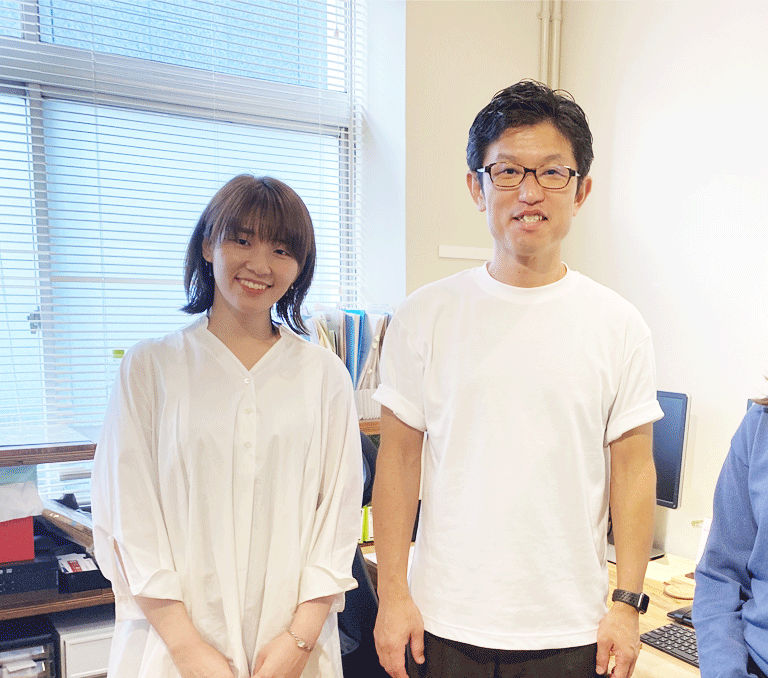このように、店舗を開業するにあたり消防法についてを初めて耳にされるオーナーの方は多いのではないでしょうか。消防法は店舗を運営するにために必ず知っておくべき法律です。
消防法の基準を満たしていないと、店舗を開業できないや罰金、営業停止になるなんてこともありえます。この記事では店舗の開業で必要な消防法の知識を解説していきます。
また、消防法と同じく重要な「内装制限」に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。これから店舗開業をご検討されている方はこちらも合わせてご参照ください。
店舗の運営に関わる消防法とは

消防法を簡単にまとめると、災害から生命や身体、財産を守る法律です。店舗の運営にあたっては火災の予防・警戒、災害や火災からの被害を軽減することに努めなければなりません。そのため、飲食店を運営する上では、以下の3つがが義務付けられています。
- 「設置しなければならない3つの消防設備」
- 「開業前に提出が必要な5つの届出」
- 「防火物品の使用」
消防法を守らないとどうなる?

消防法で定められている設備を設置しない、消防署に届け出を出さないなど、消防法の義務を怠ると法律違反となり、営業停止や罰金などになる可能性があるので注意が必要です。罰則の内容は様々ですが、軽いものでも30万円から50万円以下の罰金、もっとも重い罪は300万円以下の罰金や、懲役もありえます。
また、万が一ですが火事を起こした際に、消防法を守っていない状態でお客様に怪我などを与えてしまった場合、業務上過失致死傷罪に問われてしまうこともあります。お客様の安全を守る立場として、消防法は必ず守りましょう
店舗に必要な消防法3つの設備
飲食店を運営するにあたり、「消火設備」「警報設備」「避難設備」を設置する必要があります。3つの設備は、基準が設けられており、飲食店の規模によって設置の有無が異なります。特に、火を扱う飲食店は、基準が厳しく設けられているので注意が必要です。
①消火設備

消火設備は以下6つの項目から成り立っています。消火設備は、火災が起きた際に水や消火剤を用いて、消火をスムーズにおこなえるようにする設備のことです。6つの項目それぞれに基準が設けられており、基準に当てはまる場合のみ、設備の設置をする必要があります。
②警報設備

警報設備は、以下5つの項目から成り立っています。火災が起きた際や火災が起きそうな場合、消防署や近隣に知らせるのが警報設備です。警報設備を設置することにより、火災を未然に防ぐことができたり、火災の被害を最小限に抑えることができます。警報設備も消火設備と同様に、それぞれ細かく基準が設けられています。
③避難設備

避難設備は、以下2つの項目から成り立っています。災害時にスムーズに避難ができるように使用する器具や、避難経路を案内する標識を設置するのが、避難設備です。2階以上の飲食店で、収容人数が50人以上の場合、必ず避難器具を設置しなければならないなどの決まりがあります。また、全ての店舗や飲食店は、避難口誘導灯と通路誘導灯を設置する必要があります。
店舗の開業前に必要な消防法の届出4つ

飲食店の開業前に、消防署へ提出しないといけない届出は、主に4つ。消防法で義務付けられている4つの届出を、飲食店を開業する前に出さないと、消防法に引っかかってしまいます。営業停止処分や罰金に繋がることもあるため、注意が必要です。この章では、消防法で義務付けられている4つの届出について解説していきます。
①消防用設備等設置届出書
消防法で義務付けられている3つの設備を、基準に沿って設置したことを証明する届出が、消防用設備設置届出書です。届出を管轄の消防署へ提出し、消防検査の日程を決める流れとなります。後日おこなわれる消防検査が問題なく完了し、検査済証の交付がなされたら、終了となります。消防検査をおこなう際の重要な届出となるため、間違いなく記入することが重要です。
②防火対象物使用開始届出書
飲食店を開業する際、建物を使用開始する7日前までに、提出しなければならないのが、防火対象物使用開始届出書です。「誰がどのようなお店を開業するのか」や「消防設備等が基準に沿って設置されているか」など、防火上の問題がないかをチェックする書類になります。
消防署が定めているフォーマットに記入し、以下の書類を添付した正副2部を消防署へ提出する必要があります。消防署によって多少違いがある可能性があるため、事前に管轄の消防署に問い合わせてみると良いでしょう。
・建物配置図
・各階平面図(消火器の設置箇所を明示する)
(部分使用開始の場合は、該当区画の詳細平面図)
・建物立面図
・内装仕上表
・火気設備の機器リストと仕様書
・消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)
③火を使用する設備等の設置届出書
火災を発生させる恐れのある、火を使用する設備を設置する際に、提出しなければならないのが、火を使用する設備等の設置届出書です。飲食店では、当てはまる設備が多いため、必ずチェックする必要があります。
届出が必要な設備の例が以下になります。他にもさまざまな規定があるため、管轄の消防署に相談しながら、届出書を作成するのが良いでしょう。
・入力合計が350キロワット以上の厨房設備
・ボイラー
④防火管理者選任届出書
火災の発生を防ぐことや、火災が起きた際、被害を最小限に抑える対策を考える、役割を担う人を決めるのが、防火管理者選任届出書です。防火管理者は、「乙種防火管理者」と「甲種防火管理者」2つの種類があり、店舗に規模や収容人数によって取るべき種類が変わります。
→防火対象物の延べ床面積が300平方メートル以上かつ収容人数30人以上の店舗
・乙種防火管理者
→防火対象物の延べ床面積が300平方メートル未満かつ収容人数30人以上の店舗
・防火管理者の選任不要
→収容人数30人未満の店舗
収容人数は、お客さまだけでなく従業員も含むので、注意が必要です。甲種・乙種どちらも講習のみで習得するため、開業前に時間を確保しておく必要があります。講習が開催される日程も決まっているので、事前に管轄消防署のホームページを確認すると良いでしょう。
・乙種防火管理者(1日で約5時間の講習)
防火管理者に選任された後は、消防計画を作成し、所轄の消防署に届け出る義務があるため、事前に確認しておいてください。
店舗の開業で守らなければならない防炎物品

消防法で定められ、かつ防炎性能基準を満たしたモノを防炎物品と呼びます。基本的に飲食店を運営する上では、防炎物品を使用する必要があるため、必ずチェックしておきましょう。飲食店の運営において、防炎物品にしなければならないモノは、以下です。3つをしっかり頭に入れ、消防法の検査で引っかからないようにしてください。
・布製ブラインド
・じゅうたん
飲食店と消防法の関係
消防法を理解する上で火を使うことの多い飲食店との関わりについても抑えておきましょう。飲食店では定期的な消防器具の点検もありますので注意が必要です。
消化器具の設置義務

飲食店は以前まで、2019年10月1日に法改正があり、面積に関係なく火を使う飲食店に消化器具の設置が義務付けられました。また、IHや電子レンジは「消防法」が定める「火を使う器具」には該当しませんが、自治体によっては消化器具の設置が義務付けられる可能性がありましので、各自治体に確認するようにしましょう。
飲食店の定期的な消防器具点検

飲食店は不特定多数の人が出入りするため、半年に1回の機器点検と1年に1回の総合点検、報告を行わなくてはなりません。万が一点検報告をしなかった場合は、「点検報告義務違反」になり、30万円以下の罰金または拘留になる可能性がありますので、注意しましょう。
まとめ

この記事では、店舗の開業で必要な消防法の知識を解説してきました。以下の重要ポイントを抑えて店舗作りから開業までをスムーズに行ましょう。
弊社TO(ティーオー)は、内装を得意とするデザイン事務所です。お客様に対して真摯に向き合い、お客様に最適なプランニングをしております。
私たちにご相談いただくお客様の中には、店舗デザインに関わったことがない方も多くいらっしゃいます。店舗デザインだけでなく今回の記事の様に、開業に関するご相談にものらせていただきます。
その他、これから店舗を開業される方、テナント契約時をされる方向けのコラムををまとめています。ぜひこちらも合わせてご参照ください。