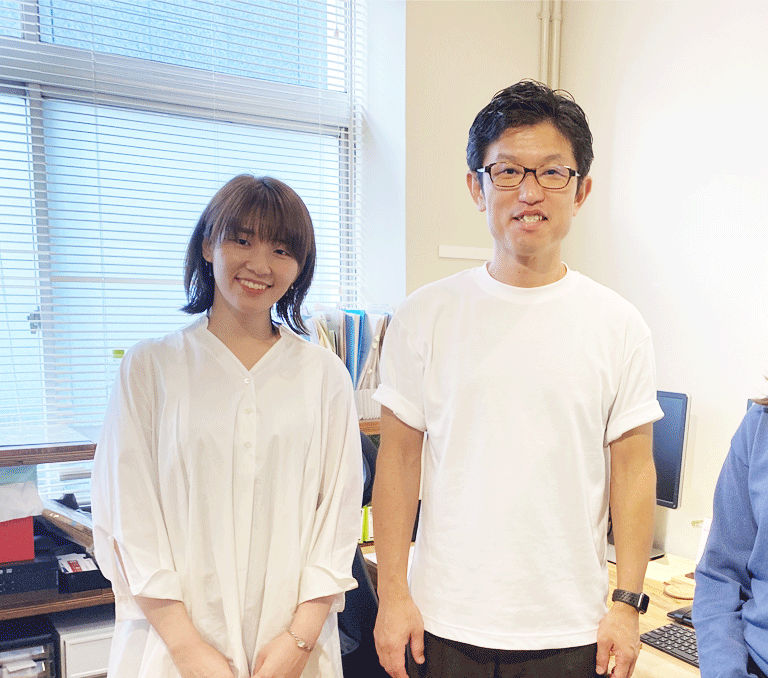飲食店を営業するにあたり営業許可証が必要になります。最近では焼肉店や焼鳥店などお肉を扱う店を構えたオーナー様がセントラルキッチンの要素を取り入れる方法をとる方も多くいらっしゃいます。
その場合、保健所から食肉販売業の許可証を取得する必要があります。食肉販売業を取るためには厨房区画にも細かな決まりがあり、内装設計をする時にあらかじめ気をつけておかなくてはなりません。今回は保健所で精肉販売許可証を取るための厨房区画の注意点をまとめて紹介いたします。食肉販売業を取る予定でお困りの方は是非最後までご覧下さい。
また、2022年ウィズコロナ時代の店舗改装リニューアルや新規出店の記事やコラムはこちらでまとめています。こちらも合わせてご参照ください。
食肉販売業とは?

食肉販売業とは主に鳥獣の肉類を販売する場合に必要な許可証です。基本的に食肉販売業を持っていることで、生肉の販売が可能となりますが、食肉販売業の許可証でできることや、できないことの制度は各自治体ごとに異なります。
例として、愛知県名古屋市で主に肉を取り扱うセントラルキッチンの場合、食肉販売業が必要となります。さらに、ハムなどにして、加工や味付けを行い梱包して販売する場合、そうざい製造業という別の許可証が必要となります。
お肉の扱い方でも販売の許可証の種類が変わるので注意が必要です。まずはご自身の営業する場所の保健所に相談してみましょう。愛知県名古屋市でセントラルキッチンをお考えの方はこちらのサイトをご参照ください。
【名古屋編】セントラルキッチンの設計で気をつけることとは?必要な空間や条件ってなに?
https://www.tototo.biz/staffblog/nagoya_design_of_the_centralkitchen/
【高山市最新版】保健所で食肉販売業の許可をとるために厨房区画や注意点をまとめました。

先ほどのご説明したように、食肉販売業は各自治体において内容が異なります。今回は、コロナ渦でも店舗の改装が多くみられる岐阜県高山市の食肉販売業に関する法律をもとに、最新の改正内容をご紹介していきます。
“高山市で飛騨牛などの食肉販売を考えている”
“セントラルキッチンの要素を取り入れたお店を開業したい”
とお考えの方は是非最後までご覧ください。
パターン1:時間ごとに”飲食店の営業時間”と”処理の時間”を分ける場合

・通常は焼肉店や焼鳥店として、飲食店の営業を行う。
・お客様がいないオープン前や営業時間後の営業時間外を利用して処理や加工を行う。
上記のように、時間ごとに業務内容をしっかりと分ける場合、厨房区画はそこまで厳しく注意する必要はありません。
基本的な考え方として、営業時間外は、処理等を行う従業員しか店内にいないため、お店全体が区画されていることになります。そのため、厨房内や精肉販売スペースを区画するための密室をつくるは必要はありません。
内装設計の決まりとして、厨房内や精肉販売スペースの扉は、スイング扉や天井まで壁がなくても良いとされています。この営業時間外に行うことは、あらかじめ保健所に申請しておく必要があります。
その方法として食肉販売許可申請時の書類の中の工程を記入する部分に、時間帯の指定を明確にすることを一緒に記載しておけば申請は完了となります。また、申請の方法やレイアウトで気になる点がある場合は早めに保健所に確認を行うことをオススメします。
パターン2:お店の営業時間内(お客様がいる時間帯)に処理や加工を行う場合

お店の営業時間内(お客様がいる時間帯)に処理や加工を行う場合、厨房区画はしっかりと天井までの壁や扉の区画を行う必要があります。
パターン1とは反対にお店の営業時間内に行うということは従業員以外にお客様もいるため普通の内装設計では密室扱いになりません。人が多いことで汚染区域としてみなされてしまうので、設計する場合は厨房内や精肉販売スペースの区画をしっかりと天井につけて計画しなければなりません。
食肉販売業の許可証をお考えの方は、今回ご紹介した2つのパターンどちらに該当するのかを設計段階で決めておきましょう!
まとめ

今回は食肉販売業についてと、高山市の保健所で食肉販売業の許可をとるために厨房区画と注意点についてご紹介していきました。食肉販売業の制度は各自治体ごとに違うため、あらかじめ調べておくことが重要となります。わからない場合は保健所に早めに相談しておきましょう!
株式会社TOは、飲食店やオフィスなど、商業施設の店舗デザインを得意とするデザイン設計事務所です。役に立つデザイン設計事務所をモットーにお客様にとって「心地よい空間とはなにか」という問いに対して真摯に向き合い、お客様に最適なプランニングをしております。何かお困りの際はお気軽にご相談ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。